 ノラ
ノラ帝政ローマって、やっぱりアウグストゥスと五賢帝だよね~あの時代にあれだけ長い期間”ローマの平和”を実現したってすごい!



そうだね。でもそのパクス・ロマーナ(ローマの平和)の裏側には、実は表舞台ではあまり名前を聞かないのに“地味にすごい”皇帝がいるんだ。



えっ、誰?



アウグストゥスの後を継いだティベリウスだよ。教科書にに名前だけ出てくることもあるけど、帝国の基盤を固めた重要人物なんだ。今日は【地味だけど実はすごい】シリーズで、ティベリウスを紹介するよ。
ローマ史に埋もれがちな皇帝ティベリウス
実は帝国の基盤を固めた“地味にすごい皇帝”
帝政ローマといえば、実質的な創始者アウグストゥス(オクタウィアヌス)、暴君ネロ、五賢帝、キリスト教迫害で知られるディオクレティアヌスなどが有名ですが、これらの有名皇帝たちの陰で帝政ローマを確実なものとした皇帝がいました。
それが、ティベリウス(在位:14〜37年)。帝政ローマ第2代皇帝です。
アウグストゥスの後継者として即位しましたが、後世の知名度は低く、古代史料でも「暗い皇帝」「暴君」と評されがちです。
しかし実際には、彼の堅実な統治こそが「パクス・ロマーナ(ローマの平和)」と呼ばれる黄金期の土台を築きました。


ティベリウスとは
名門クラウディウス家に生まれて
紀元前42年、ティベリウスは名門クラウディウス家に生まれます。アウグストゥスがティベリウスの母リウィアを見初めたことにより母リウィアは実父クラウディウス・ネロと離婚し、アウグストゥスの妻となります。この時既に生まれていたティベリウスと、妊娠中のリウィアのお腹の中にいた弟ドルススは、実父クラウディウス・ネロの死後にアウグストゥスに引き取られ、養子として育ちます。
(アウグストゥス、地位を利用して既婚女性を奪うとは・・・)
軍人としての輝かしい経歴
ティベリウスは若くして軍に入り、ゲルマニア遠征やパンノニア反乱鎮圧で大きな戦功を挙げました。規律を重んじ、冷静沈着に軍を指揮する姿から、兵士たちに深く慕われました。
複雑な後継者争いを経て皇帝へ
アウグストゥスは複数の後継者を立てましたが、次々と早逝。
最終的に残ったのがティベリウスでした。
本人はもともとウィプサニアという女性と結婚し小ドルススをもうけるなど幸せな生活を送っていましたが、アウグストゥスにより後継者に指名されると無理やり離婚させられ、アウグストゥスの娘ユリアと結婚させられることになります。
その上、ティベリウスは政治を好まず、人前で話すのも得意ではなかったと言われます。
それでも西暦14年、アウグストゥスの死により第2代皇帝となりました。
”暗い”イメージの皇帝
ティベリウスを知っている人の中には、”暴君””冷徹な人””地味”といったイメージを持つ人もいるのではないでしょうか。
ティベリウスの性格
ティベリウスは、人前で称えられる、華やかな”皇帝像”と真逆の性格をしていました。
人前に立つのを嫌い、華やかさよりも実直さを重んじました。
複数回の隠遁生活
その性格も相まってか、ティベリウスはその生涯で何度か”隠遁生活”をしています。
分かりやすいのは2つ。
アウグストゥスの娘ユリアとの結婚生活がうまくいかなかったときにロドス島に隠遁したり、ティベリウスの治世の後半には息子小ドルススの死や陰謀などに疲弊し、政務から距離を置くためにカプリ島に隠遁したりしました。
”恐怖政治”のイメージ
彼がカプリ島に隠遁した隙を狙って、近衛長官セヤヌス(セイヤヌス)が権力を掌握してしまいました。
政敵を次々と排除し、恐怖政治を敷きました。
ティベリウス本人の意思にかかわらず、「ティベリウスの治世=恐怖政治」というイメージが強まってしまいました。
古代史料が描いた暗い逸話
また、歴史家のスエトニウスやタキトゥスは、ティベリウスを「猜疑心に満ちた冷酷な皇帝」と描きました。
カプリ島で放蕩にふけり、客を断崖から突き落とした――そんな逸話まで残ります。
もちろん誇張や偏見を多分に含むものですが、後世における彼の評判を暗くする要因となりました。
実は堅実な“実務皇帝”
このような”暗い一面”が目立って伝わってしまったティベリウスですが、実際の治世はどうだったかというと、実はとても堅実な皇帝で、その手腕によりアウグストゥスが築いた”帝政ローマ”を盤石なものとしたのです。
拡張よりも国境防衛を重視
ティベリウスは征服戦争を避け、帝国の安定を第一に考えました。
ライン川やドナウ川沿いに要塞を築き、兵士を現地に定住させて国境防衛を強化。
東方ではパルティアとの戦争を外交で回避しました。
派手な戦果はなかったものの、この「守りの戦略」が帝国を二世紀以上にわたって安定させます。
財政を健全化
彼の功績は軍務だけではありません。
アウグストゥス時代の華やかな事業で疲弊した財政を徹底的に立て直しました。
浪費を嫌い、属州には「羊は刈るが皮は剥がない」として重税を禁じ、皇帝財庫には巨額の余剰金が積み上がります。
その上、皇帝主催の戦車競技会を中止したりと、見栄えを全く気にすることのない財政引き締めを行ったりもしました。
その堅実な財政基盤は、後のローマの黄金期を下支えしました。
属州統治の安定化
広い帝国領の統治にも心血を注ぎました。
属州には有能な総督を長期任命し、法の支配を徹底。
反乱が起きても最小限の軍で鎮圧できる体制を築きました。
道路や水道といった公共事業も進め、属州民に「ローマ人としての生活」を根付かせることで、帝国を持続的に運営するモデルとなったのです。
人気はなかったが…
こうした功績が地味だっただけではなく、アウグストゥスのような盛大な祭典や施しを行わなかったため、民衆からはティベリウスは「冷たい」「地味」と受け止められがちでした。
しかしティベリウスは、人気取り政策には見向きもせず、アウグストゥスが築いたローマを確実のものとするために、誰よりも長い目で、広い視野で施策を実行することを心掛けていたのでしょう。
そういった彼の志は、民衆や元老院からの不人気という結果さえも受け入れられるほど強かったのではないでしょうか。
暗さと偉大さを併せ持つ皇帝
ティベリウスの治世には確かに陰の部分もありました。彼自身の性格、そしてセヤヌスの暴走など。
しかしその一方で、彼が築いた財政の健全化、国境防衛の体制、属州統治の合理化は、のちの「パクス・ロマーナ(ローマの平和)」を可能にした大きな基盤となりました。
歴史をどう読むか
スエトニウスやタキトゥスが残した史料は、当時の政治的立場や感情を強く反映しています。
史料を鵜呑みにすれば、ティベリウスはただの「暗い皇帝」になってしまうでしょう。
けれども多角的に読み直せば、彼は「地味だけど実はすごい皇帝」として再評価できるということは忘れてはいけません。



ティベリウスって、ほんとに名前も知らなかったけど、すごい皇帝だったんだね。
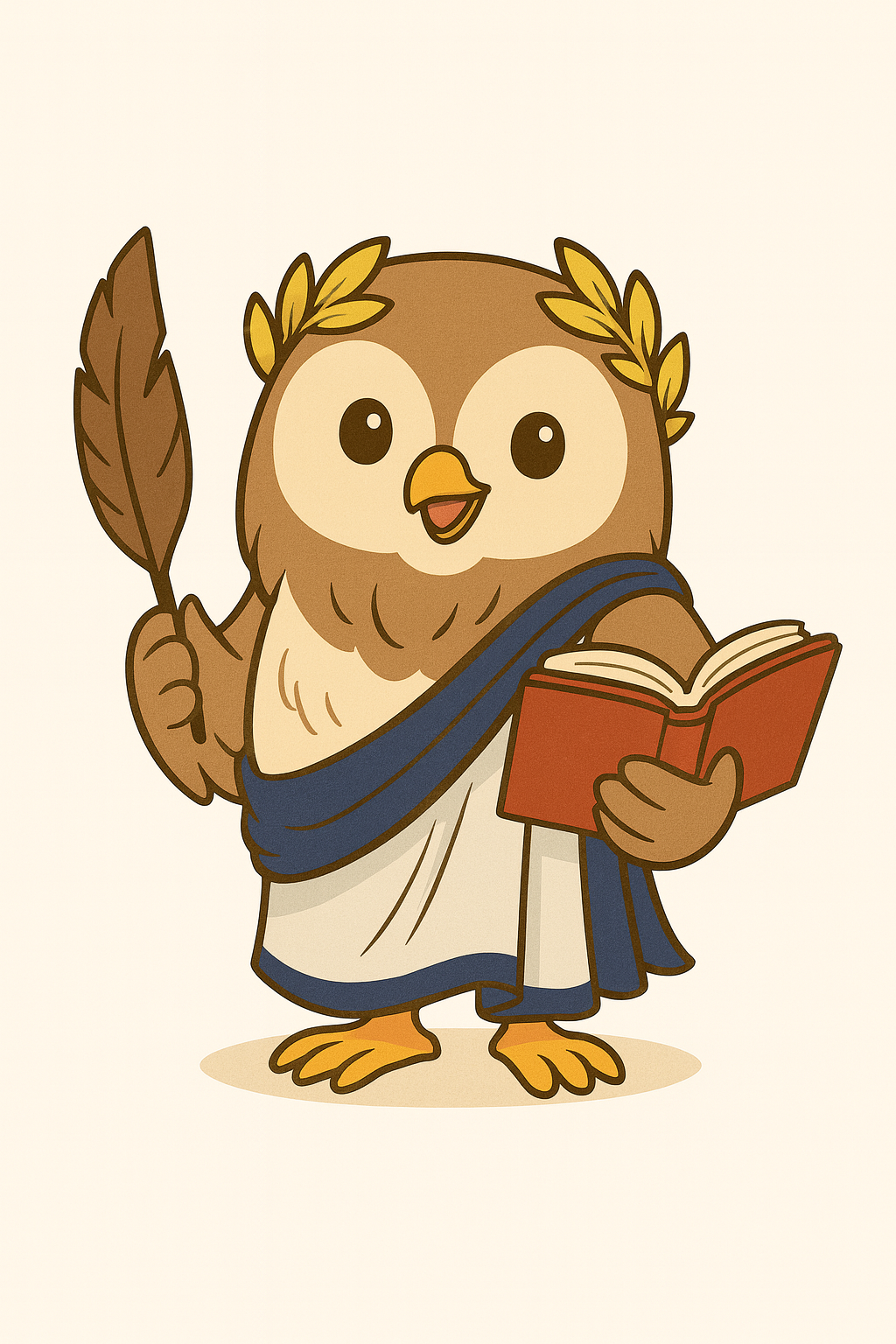
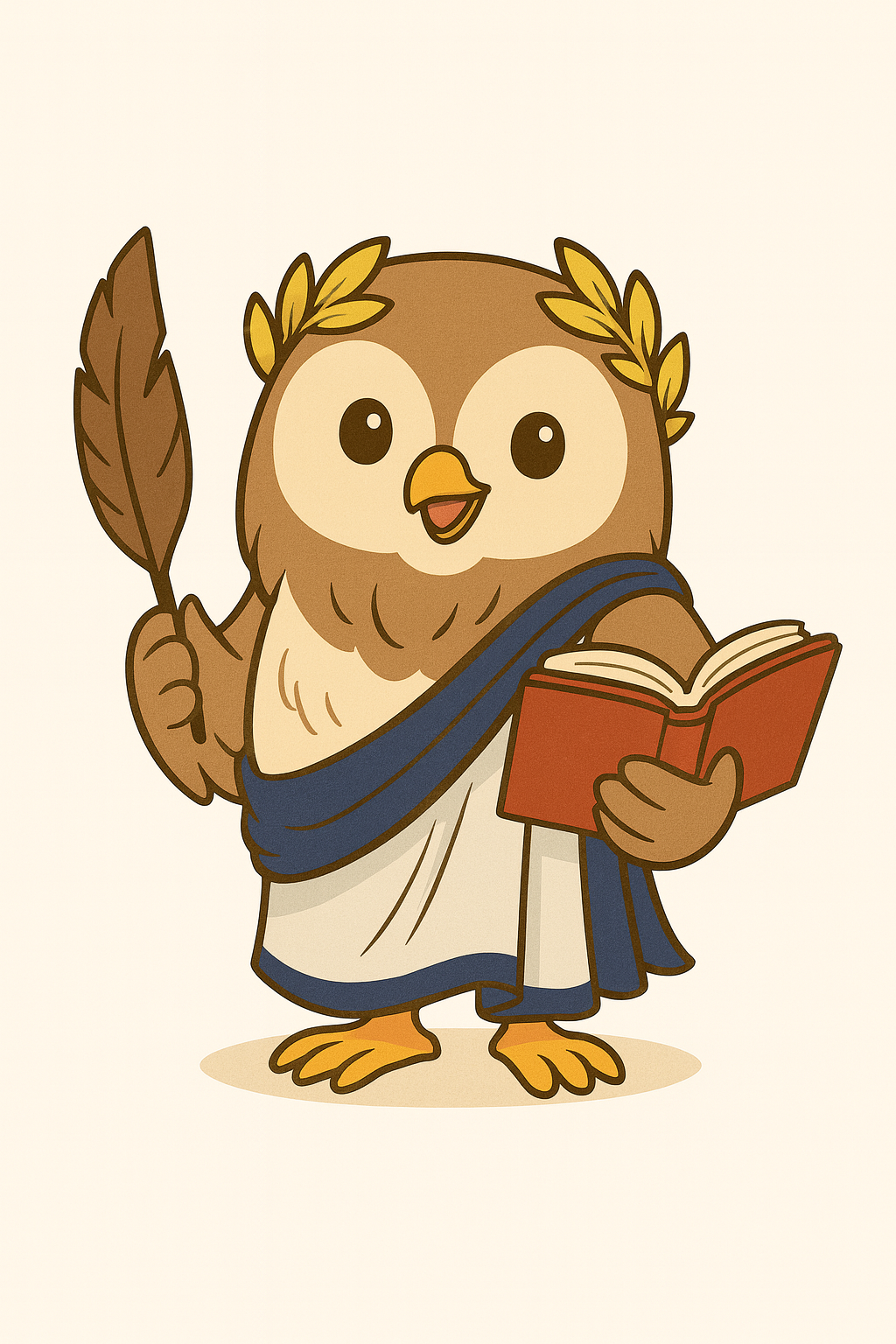
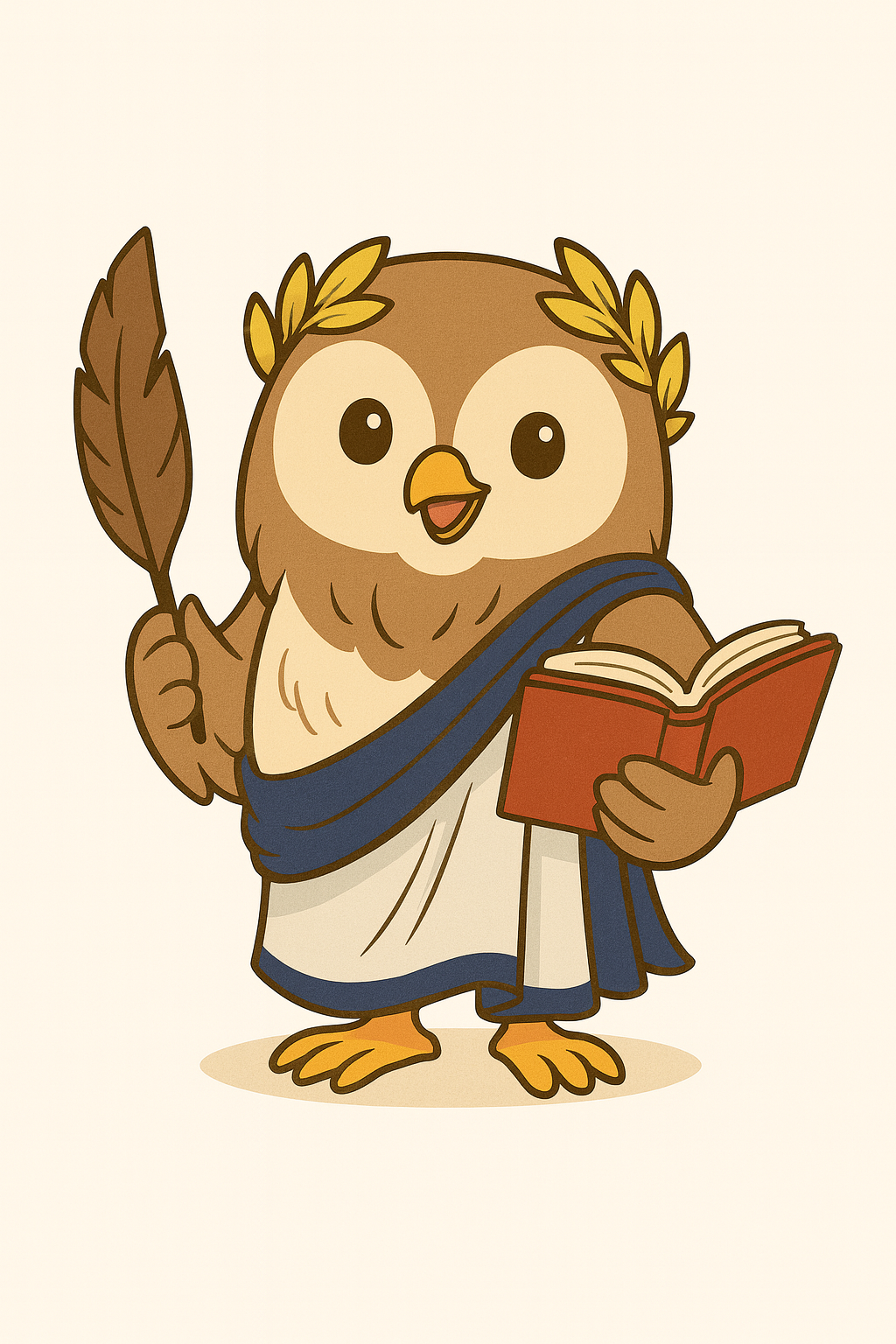
そうだね。地味で人気はなかったけれど、その堅実さがローマの黄金期を支えたんだ。



堅実に未来を見据えた政治をしたティベリウス、私はとても好きになったよ。
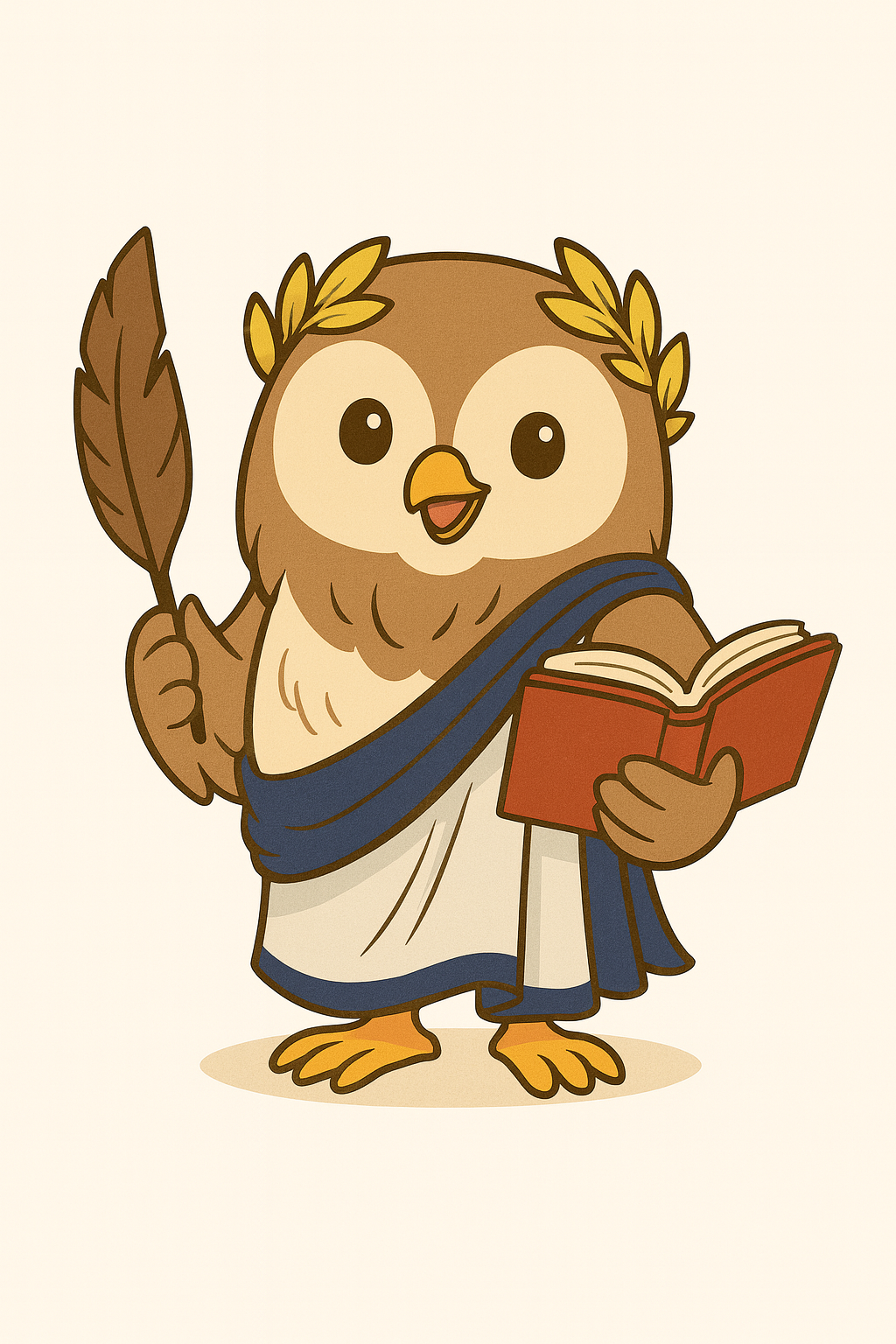
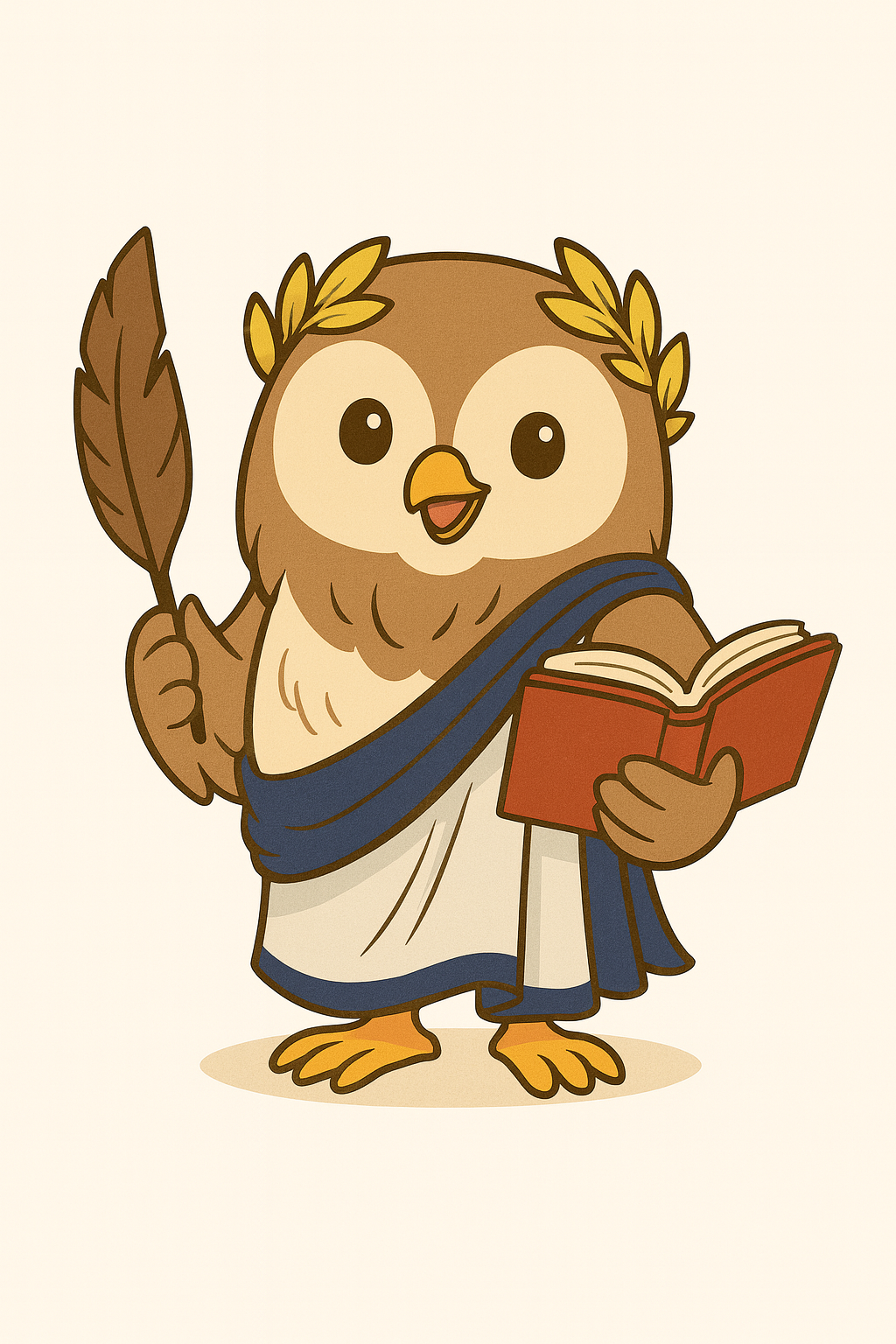
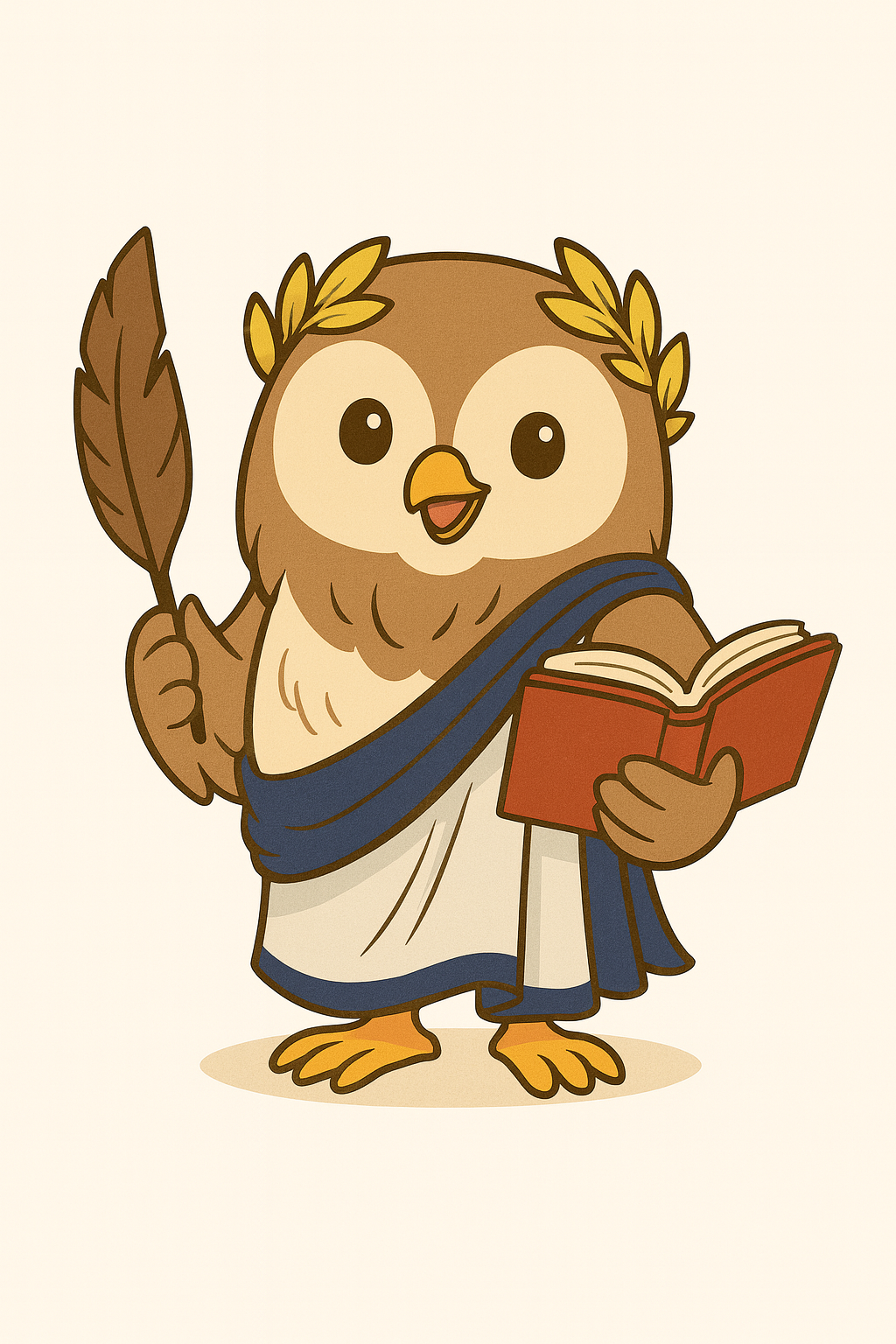
うん。歴史は、派手な人物だけじゃなくて、こういう“見えない支え役”にも目を向けるともっと面白くなるんだよ。これからも、史料を多角的に読む、という観点から話をしていこうと思うよ。
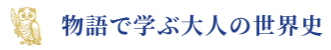



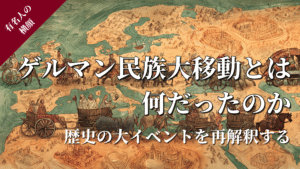



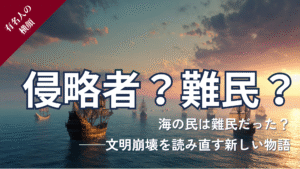
コメント